【 コラム 】カテゴリー記事一覧
2023年4月11日
子どもたちに 平和な未来を 〜兵器ではなく文化を〜
人形劇団プークは1929年の劇団創立以来、民衆の平和を願って活動してきました。しかし、太平洋戦争時には治安維持法(戦後に悪法として廃止)によって劇団代表者がいわれのない投獄を経験しています。そして今、「非戦国」から「交戦国」になりかねない防衛費倍増を推し進める日本政府の政策に強い懸念を持ち、断固反対の意思を表明します。
非戦国の我が国が「反撃」「防衛」という言葉の曖昧な拡大解釈によって「実質交戦国」に向かおうとしている事は、明らかな憲法違反です。
また日本政府は、数年での防衛費倍増を大国の大統領に約束し、世界情勢を背景に国民にも自覚と責任を求め、増税を正当化しようとしています。しかもその財源は不確実かつ不明瞭なものばかりで、将来のさらなる増税は想像に難くありません。
さらに、太平洋戦争開戦の大きな財源になった反省から、戦後は決して認めなかった建設国債の防衛費予算化への検討が進められています。これは国の大きな方針転換であり、再び「戦争を行う国」になりかねず、決して看過できません。
私たちは一年前に、権力者が判断を誤ればいとも簡単に戦争が起こってしまう、というロシアのウクライナ侵攻を経験しました。悲しいことに現在も戦争は終結していません。未来の我が国を担う子どもたちの平和を守らなければなりません。平和を維持し文化を豊かにすることに国の力が注がれるよう、私たち人形劇団プークは、強い意志をもち、反戦・平和の声をあげ続けます。
ー 人形劇団プーク代表 栗原弘昌 ー
(2023年4月1日発行 みんなとプーク No.283新年号 『プー吉は進む』より)
2023年1月1日
伸びやかに 願いを込めて
新年あけましておめでとうございます。
今年プークは創立94年を迎えます。長い活動の中でも、この三年間は困難と厳しさの連続でした。コロナウイルスによる活動への影響は、未だ終わる気配はありません。
しかし得たものも少なくありません。対処の仕方も向き合い方もだいぶ変容してきました。オンラインや配信といった手法で、私たちの舞台を伝える方法も広がり、初めて人形劇に触れる人々とも出会えました。しかし、やはり観客の息づかいを感じながら、マスク越しであっても、観る人の笑顔に勇気づけられながら届けられる、生の舞台は格別なものだと、あらためて強く感じています。そして、三年ぶりにやっとプークを観られました、と全国各地のかたがたの嬉しい声をいただき、喜びを共にできる事が私たちの大きな原動力です。
この三年間のコロナ禍で、子どもたちはたくさんの我慢や分断を強いられてきました。いつの時代も子どもたちは、この世に生まれてから3歳を迎えるまでの間に、めざましい成長をとげてゆきます。この3年という年月は、それぞれが自我を確立してゆき、個性あふれる「ひと」になっていく大切な時間です。すべての子どもたちが、限りない可能性を奪われることなく、どうか伸びやかに心ゆたかな人として育つことを、願ってやみません。その思いを込めて、私たちは人形劇で心揺さぶる時を届ける、真摯に舞台創造に向き合い続ける集団でありたい、と思います。
春三月にはプーク人形劇場にて、新作「ねこはしる」を上演します。「生きることはつらいかもしれないけれど、生きているからこそ感じられる喜びは、何事にも代えられない。」日々を生きづらいと感じている若者たち、おとなたちに、エールを贈る舞台として新境地を目指します。
今年も、ご支援をよろしくお願いいたします。
ー 劇団プーク 代表 石田伸子 ー
( 2023年1月1日発行 みんなとプーク No.282 新年号 『プー吉は進む』より )
2022年10月30日
第32回イーハトーブ賞を受賞しました!
岩手県花巻市創設の、第32回イーハトーブ賞をプークが受賞しました!
9月22日、花巻市での贈呈式には劇団代表の栗原弘昌と井上幸子が出席、人形映画『セロ弾きのゴーシュ』の映像資料なども交えた講演も行いました。賢治生誕の地で、賢治を愛する皆さんと貴重な交流をさせていただきました。

第32回宮沢賢治賞・イーハトーブ賞贈呈式の様子
イーハトーブ賞受賞によせて
人形劇団プーク代表 栗原弘昌
今夏8月、岩手県花巻市創設のイーハトーブ賞受賞の知らせが入りました。イーハトーブ賞とは「宮沢賢治の名において顕彰されるにふさわしい実践的な活動を行った個人または団体におくられる。」(宮沢賢治学会イーハトーブセンターHP)とあります。それは突然舞い込んだ大きな喜びと大きな驚きであり、劇団全体に活力をもたらしてくれる出来事となりました。
選考理由には、宮沢賢治生前の1929年に劇団を創設し、1948年の再建第一作や劇団の節目に「オッペルと象」を公演している事。1953年には長篇人形映画「セロ弾きのゴーシュ」を制作し、それぞれの作品が農民や民衆からの視点で描かれている事があげられています。一作品の評価というよりも、劇団創立から現在までの活動に対しての評価であると理解すると同時に、今後の創造活動に対する責任を感じました。また、どのような形で社会に貢献していくべきか、明確な意思をもって取り組まなければならないと身の引き締まる思いでいっぱいです。そして、長年にわたりプークを応援し劇団を支えて頂いた全国の皆様に、改めて感謝の気持ちをお伝えしたいと思います。
賢治没後の1934年に手帳の中から発見された有名な「雨ニモマケズ」は、2011年の東日本大震災後に、復興に取り組む東北の方々の心の支えにもなったという話を聞いたことがあります。時を越えて人々の心に影響を与え、生きる力を与えてくれる宮沢賢治作品の多くがそうであるように、我々もそのような作品創造を目指し、今回の受賞に誇りをもって、そして謙虚に一歩ずつ一歩ずつ進んでいきたいと思います。(2022年10月1日発行「みんなとプーク」第281秋号掲載の『プー吉は進む』より)




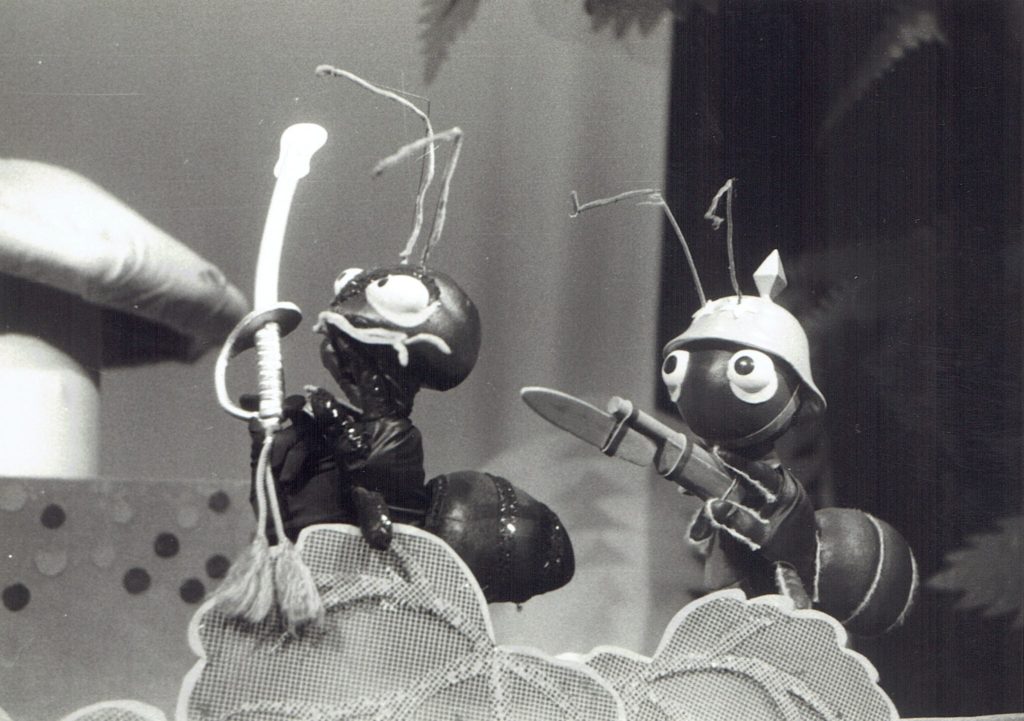



立派な賞状と正賞の「空のクリスタル」は11月公演期間中、プーク人形劇場にて展示予定です。ご観劇へお越しの際にはぜひご覧になってください。「空のクリスタル」については、宮沢賢治学会イーハトーブセンターHPに詳しく解説されています。
2022年9月7日
プーク人形劇場誕生50周年シリーズ⑭
本日より始まりました「新宿ストリートシアター」。5つのバリアフリー(国籍・障害・年齢・経済・地域)をコンセプトに、普段なかなか劇場に足を運べない方や、今まで舞台芸術に出会ったことのない方にも、優れた芸術体験をお届けしたい。そんな想いから、今年はプーク人形劇場・新宿高島屋・オンラインの3拠点で開催しています。
「いつもの場所」が「劇場」に! 会場で、オンラインで、皆さまのお越しをお待ちしております。
そしてこちらのコラムでは、およそ50年前の劇場誕生時から構想され、これまで長きにわたって続けられてきた「世界の人形劇シリーズ」の歴史についてご紹介します。プークは劇団創立時より、世界各国との文化交流や国際活動を積極的に行ってきました。その一環として始められたこの劇場企画ですが、プークの定本「現代人形劇創造の半世紀ー人形劇団プーク55年の歩みー」(編著者/川尻泰司、未来社刊)には、そのいきさつが詳しく記録されています。

第4部1971~1980(竹内とよ子、三橋雄一・著)
5,国際交流から国際活動へ
「世界の人形劇シリーズ」スタート
プーク人形劇場企画・世界の人形劇シリーズが始まったのは、1973年11月である。以後、このシリーズは毎年プーク人形劇場の名物となっている。その第1回の出演は、イギリスのパーシー・プレス父子の『パンチとジュディ』ならびに吉田千代勝・千代海の秋田猿倉人形芝居という日英両国の伝統人形劇の競演だった、この取合せは実は1972年に手合せずみだった。日本ウニマ代表団がシャルルビル・メジェールに向かう途中、当時のウニマ会長ジャン・ブッセル宅をロンドン郊外に訪ねた。そこでパーシー・プレス一座と吉田千代勝一座とがサロンで上演したのである。




また、1973年4月には川尻が芸場支配人長谷川正明を同行して、ウニマ執行委員会(ストックホルム)とソフィアの国立中央人形劇場25周年記念行事に出席した。その後、川尻はモスクワの国立中央人形劇場に、以前から約束してあったプー吉の人形を寄贈して帰国したが、長谷川は川尻と分かれて40日間にわたって、ヨーロッパ各地に人形劇の視察旅行を続けた。そのような事前の調査や視察の上に、『パンチとジュディ』を皮切りに第2回、アルブレヒト・ローゼル(西ドイツ)第3回、ブルガリア国立ソフィア中央人形劇場、第4回、リチャード・ブラッドショウ(オーストラリア)とジャン・ポール・ユベール(フランス)、以下今日に至るまで、このシリーズが続けられている。








回を重ねるにつれて、プーク人形劇場でこのような海外人形劇紹介して行なわれていることは、プーク 国内だけでなく海外においても国際的劇団として知らしめることになって行った。 巻末のプーク公演・ 活動年表を見ても分るように、プーク以外のところでも、海外人形劇人の来日とその公演が繁くなったのは1974年以降であり、プーク人形劇場で上演はしなくても海外人形劇人のプーク訪問も同時期から増えている。 このことはプーク人形劇と世界の人形劇シリーズの継続が全く無関係とは言えないだろう。
一方で、ウニマ執行委員として川尻は、第2回中央アジア人形劇フェスティバルに招待参加 (1975年)し、 また、星野はオーストラリアのタスマニア人形劇場で、自作のプーク上演作品『とんまなてんぐ』 (英訳名 BIG NOSE) 演出・美術を担当、二カ月間にわたって同劇場の若いアンサンブルを指導した。

そして、1976年6月、第12回大会と国際人形劇フェスティバルがモスクワで開催された。これには、プークからはまたも8名(ノーヴァからも嘱託の酒井久美子と同野公夫を含む)が参加した。このモスクワ行きは、日本代表は69名の多数にのぼった。 大会では川尻泰司は、執行委員に再選されたほか、新設された第三世界委員会の委員にも選ばれた。また、この大会と祭典参加で、長谷川、曽根、竹内の3名は、3コース に分れたそれぞれのツアーの事務局を、川尻原次はフェスティバルに上演参加の八王子車人形西川古柳座と西畑人形、池原由起夫夫妻らの舞台監督を、秋田恭子は日本ウニマ書記として日本代表団の事務局を務めた。このモスクワ参加の年の秋、プーク初の海外公演が行なわれた。
2022年7月27日
プーク人形劇場誕生50周年シリーズ⑬
皆さん、こんにちは。暑い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。人形劇団プークでは、明日から夏の公演『エルマーのぼうけん』を紀伊國屋ホールにて行います。
プークは1965年のNHK教育テレビ『エルマーのぼうけん』放送に関わったことをきっかけに、その内容に惚れ込み同年には舞台初演を果たしました。その頃の日本は、子どもたちを取り巻く文化状況が過渡期を迎え、プークは子どもたちのためにどのような人形劇を創っていくか模索している時期でもありました。
『エルマーのぼうけん』との出会いは、その後の子ども劇場・おやこ劇場運動へもつながり、プークの活動は全国へと広がっていきました。以来、再創造を重ね、プークの大切な作品として受け継がれています。今回ご覧いただく『エルマーのぼうけん』は、2017年にアメリカ在住の原作者R.Sガネットさんのご自宅を訪ねたところからスタートし、ブルガリアの人形劇界を牽引する美術家マィア・ペトロヴァ氏をお迎えしての大プロジェクトとして誕生しました。たくさんの出会いを経て、この度ファイナル公演となります。
皆さんそれぞれに想いの詰まったこの『エルマーのぼうけん』ですが、空を飛ぶことについてのこんな見方もあるかもしれません。今月発行の 「みんなとプーク」第280夏号 『プーク見聞録』のコーナーから、ご提案いたします。こちらの記事を読まれたあとには、きっと新たな視点で『エルマーのぼうけん』をお楽しみいただけることと思います。ぜひ劇場でお待ちしております。

プーク見聞録 その6 ~空のイメージ~
「ぼくは将来ぜったい飛行機乗りになるよ」夏の波止場で少年は語る。沖には蒸汽船、激しく吹く汽笛すら水平線の彼方へ吸い込まれてしまいそうな田舎の港町。空ではただ鴎(かもめ)が鳴いている。R・S・ガネット原作による人形劇『エルマーのぼうけん』はそんな情景に始まります。有史より、人は空に焦がれ、幾度となく飛行を夢見て来ました。その憧れは神話や宗教画の図象などに残され、やがて科学技術の発達により実現されました。今回は、空や飛行についてお話しましょう。
ギリシャ神話に語られるイカロスの翼は、人間の傲慢を開示する悲喜劇であると共に、普遍的な空への憧憬を描いた一遍です。ダイダロスの作った人工の翼は、父子のみでなく多くの人々を空へと駆り立てました。11世紀の英国に実在したとされる修道士もその一人で、エイルマーという名のその若者、神話の叙述を現実と思い込み、ダイダロスに倣い細工した翼で塔の上から飛び立ったといいます。無念にもこの若者は、夢の代償に大きな怪我を負ったと伝えられていますが、このような実験例は古今東西に多く残されています。やがて時は経ち、18世紀には科学技術を応用した乗り物による飛行実験が欧州で行われるようになりました。その歴史は空を漂う気球に始まり、翌世紀の半ばには動力と舵を備えた飛行船が発明されました。この空飛ぶ船により、ついに人類は自らの意思による飛行を成し得たのです。以降、航空技術の発展は日進月歩の時代を迎え、20世紀初頭に誕生した飛行機により空は速度の百年を駆け行きました。
しかし、なぜ人は空に憧れ、そして飛びたいと望むのでしょうか。そもそも空とは何なのか。日本の場合を考えてみましょう。作家の竹西寛子は「空はずっと昔から空だった」と、いつでもそこに空があることを直感的に述べていますが、高村光太郎の『智恵子抄』には「東京には空がない」と書かれています。我が国における空(そら)は、古代、般若心経にある空(くう)の思想と結びつき、また私たちは何もないことを空(から)とも書きます。そう考えた時、智恵子の言葉は「東京には無(む)がない」とも読めるでしょう。街や道路といったものは意味によって建設され、価値によって残されます。しかし、そうした場ではただそこに在ることを許容する空白が失われます。「色のない白は最も清らかであるとともに、最も多くの色を持っています」と川端康成の言葉にありますが、様々な人間の理想や思惑が複雑に絡み合い形成される都市において、時に人は何もない空を、白の色彩を見失います。また、作家の石牟礼道子は「むかしの田園では、大地と空はひとつの息でつながっていた」と書いています。都会を離れ霞に滲む遠くの峰々を見遣る時、私にも空と大地とは一つに見えてなりません。空とはつまり、私たちの精神を意識やその理解から解放し、限りのない無垢へと至らしめる存在なのではないか。私には、そう感じられます。
「人間は考える葦である」とは、パスカルの言葉です。自然の中にあっては水辺の葦草のように頼りない人間が、これほど豊かな社会を築き上げてこられたのは、多く思考する力に依るものだと言えるでしょう。しかし、イカロスの翼の失墜は頭脳ばかりでは空を自由に飛ぶことは出来ないことを示唆しています。では、どうしたら人は自由に空を飛べるのか。その一つの答えが絵画にあります。マルク・シャガールの『誕生日』には、宙に浮かぶ画家が恋人に口づけする姿が描かれています。ここで注目したいのは、この画面には翼もそれに代わる装置も描かれてはいないことです。彼はただ、喜びにおいて飛んでいるのです。後年にシャガールは自身の絵画表現について「(私が描くのは)夢ではなく、生命」だと述べていますが、この一枚の絵には生命が歓喜する時、人は空をも飛べるのだということが描かれているようです。

2018年の夏の日に、ガネットさんが来日されました。今でも思い出すのは、紀伊國屋ホールで対面した彼女から光のようなものを感じ、我知れず落涙した記憶です。それは、初めて太陽を目の当たりにした土竜(もぐら)が、その光彩に流す涙のようでした。きっと私はこの時に空を飛んだのです。物語りの中で、少年の憧れは竜の自由と一つに結ばれ、羽ばたき出した大きな翼は空へ飛翔します。或いは、人は誰かの翼になることで本当の空を飛べるのかも知れません。明日、あなたは誰と空を飛びますか?
(文/池田日明)

